 知床白書 Shiretoko White Paper
知床白書 Shiretoko White Paper
I 知床世界自然遺産地域の管理
II 知床世界自然遺産地域の課題
III 知床世界自然遺産地域の管理状況
IV 知床世界自然遺産地域の生態系と生物多様性の現況と評価
V 知床世界自然遺産地域等の利用状況と評価
VI 総合評価
付録
1.陸上生態系
(3)ヒグマ
平成24年度の出没状況
ヒグマの目撃件数は斜里町で1,763件、羅臼町で387件と前年度よりも著しく増加し、両町ともに集計開始以降で最多となった(図IV-1, 2)。両町における年間の目撃数は、平成23年度までは7月に最も多くなるという傾向を示したが、平成24年度は8月に最も多く、9月まで多い状態が継続するという特徴を示した。8~9月の目撃には、痩身で衰弱した状態のヒグマも含まれ、当年の餌環境が近年の状況と異なり、カラフトマスの遡上時期が遅く遡上数も少なかったことが一因である可能性がある。
斜里町での目撃は、国立公園内1,576件、国立公園外187件であり、大部分が国立公園内であった。国立公園内では、人の存在を気にすることなく道路沿いや観光施設周辺に出没する特定のヒグマが、利用者とごく近距離で頻繁に目撃された。近距離での目撃に関連して、国立公園利用者がヒグマに餌を投げ与えた事例や、ヒグマに接近しすぎた観光客が威嚇され、驚き転倒して負傷したという事例等があった。また、不法投棄された生ゴミにヒグマが手を付けたという事例も確認され、マスコミによって大きく報道されるに至った。
さらに、宿泊施設のゴミ置き場に餌付いた特定のヒグマが日中出没を繰り返すという極めて危険な状況があった。国立公園外では、ウトロ市街地へ複数のヒグマが出没を繰り返し、民家敷地内の魚を乾燥させるための小屋にヒグマが夜間に侵入して荒らすという事例があった。
羅臼町でのヒグマ目撃は、国立公園内152件、国立公園外235件であり、平成19年度以降では国立公園外での目撃割合が高いという特徴を示した。公園の内外を問わず当町の目撃は、海岸沿いの住宅地周辺で多く、今年度についても倉庫や車庫への侵入があったほか、漁業者の利用が極めて多い羅臼漁港内での徘徊が発生した。また、水産加工場残渣や家庭用ゴミ箱や軒先の干し魚が荒らされるという事例が多数発生した。
ヒグマの人為的死亡個体数は斜里町で22頭(有害捕獲16頭、狩猟6頭)、及び羅臼町で45頭(全て有害捕獲)の計67頭であった。また、67頭のうちメス成獣は斜里町で8頭、羅臼町で16頭であり計24頭であった。人為的ではない自然条件下で発見されたヒグマの死体は斜里町で4体、羅臼町で2体の計6頭体と近年になく多く、当年の餌環境が近年の状況と異なっていた可能性を示唆している。
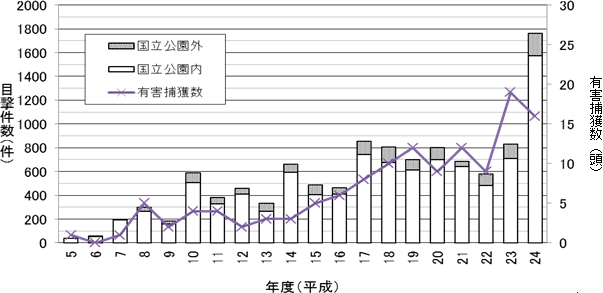
図IV-1.斜里町内ヒグマ目撃件数と駆除件数の推移
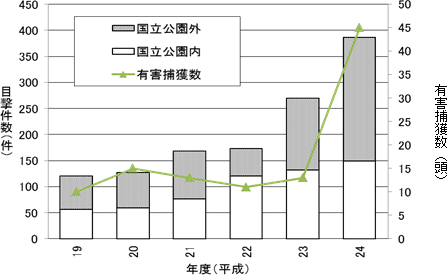
図IV-2.羅臼町内ヒグマ目撃件数と駆除件数の推移
ヒグマ個体数推定のための調査・解析業務の進捗
「知床半島ヒグマ保護管理方針」を策定した知床では、従来法よりもより精度の高いヒグマの生息個体数の推定が求められている。そのため、ヒグマ個体数推定のためのカメラトラップ調査を行うとともに、回収したデータの解析を行った。幌別-岩尾別地区14箇所とルサ地区1箇所の計15箇所において、計30台の自動撮影カメラを平成24年11月から約1ヶ月間稼働させ、動画を撮影した。
撮影数は各カメラ0~232回、のべ1416回であった。また、ヒグマによる誘引餌の消失やヒグマによると推定されるカメラの破損等のトラブルも6台あった。解析の結果、ヒグマがカメラトラップを訪れた回数(イベント数)は各地点で0~10回、計45回であり、うち24回で個体識別でき、単独ヒグマ2頭、親子2頭ヒグマ3組、親子3頭ヒグマ1組の計6組11頭が確認された。
ただし、精度の高い個体数推定を実施するためには相当な努力量を要すると考えられた。(松田裕之委員)















