 知床白書 Shiretoko White Paper
知床白書 Shiretoko White Paper
I 知床世界自然遺産地域の管理
II 知床世界自然遺産地域の課題
III 知床世界自然遺産地域の管理状況
IV 知床世界自然遺産地域の生態系と生物多様性の現況と評価
V 知床世界自然遺産地域等の利用状況と評価
VI 総合評価
付録
2.利用に関する課題
○観光客によるヒグマへのエサやりと至近距離での写真撮影
知床半島ではヒグマは、世界でも有数の高密度に生息していることから、知床を象徴する野生動物の一つとなっている。一方で大型の野生動物であることから、一歩間違えば大きな事故を引き起こす可能性を持っている。平成24年度には遺産地域を中心に年間計2,000件以上(海上からの目撃を除く)と極めて多数の目撃があった。遺産地域内の沿道では、人の存在を気にしない複数のヒグマの出没が半ば常態化していた時期もある中、観光客が車中から意図的にエサやりをした事例や、投棄された生ゴミを採食した事例のみならず、徒歩で接近して至近距離からの写真撮影を続けるカメラマンも確認された。
エサやりや近接しての写真撮影等によって人に馴れたヒグマが、観光地や隣接市街地に近づくことによって地域の安全を脅かすことにつながりかねないため、沿道におけるエサやり禁止対策やカメラマンへの適切な指導等が課題となっている。
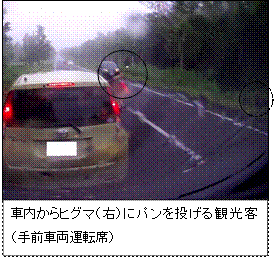
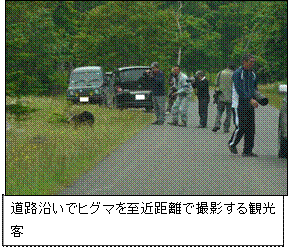
○トドと漁業との共存
知床周辺海域には、冬から春にかけてトドがロシア海域の繁殖場・上陸場から、個体群維持の上で重要な妊娠雌を中心とする群れが来遊し、越冬と摂餌を行っている。日本近海に来遊するトドの集団は増加傾向にあり、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストの見直しにおいて、絶滅危惧Ⅱ類(VU)から準絶滅危惧(NT)にランクを下げた。知床周辺海域では来遊するトドにより漁獲物を奪われたり漁網が破られるなどの漁業被害が発生しており、近年は来遊域と期間が拡大・長期化するなど、深刻な状況となっている。
今後も科学的な検討に基づく適切な管理による漁業被害の軽減と個体群の維持が求められている。

○観光のための希少猛禽への給餌
羅臼町の一部で、観光のためにオジロワシ、オオワシ、シマフクロウへの給餌が行われている。自然分布の変化や人間の生活圏への接近を促進させること、交通事故を引き起こす要因となること、感染症発生時に悪影響を拡大させること、人為的エサ資源に依存する個体が増加することなどの問題が指摘されている。
一部で給餌や観察に関するルール作りなどの改善が進められているが、根本的な解決には至っていない。
○知床岬への動力船による上陸
知床岬への観光目的での動力船による上陸は禁止されているが、依然として動力船による文吉湾への上陸行為が確認されており、上陸禁止についてより一層の周知等が求められる。なお、NPO法人や地元自治体等が主体となり、海岸漂着ゴミ対策のためのゴミ拾いボランティア事業が実施されている。参加者は関係機関、町民、観光客と様々であるが、引き続き、「知床半島先端部地区利用の心得」を遵守のうえ、実施するよう指導していく必要がある。
また、知床岬トレッキング時の復路について、小型船舶による送迎が実施されている。トレッキング時の送迎に関しても、「知床半島先端部地区利用の心得」に基づき、実施しないよう引き続き指導する必要がある。















