 知床白書 Shiretoko White Paper
知床白書 Shiretoko White Paper
I 知床世界自然遺産地域の管理の理念と目標
II 知床世界自然遺産地域の課題
III 知床世界自然遺産地域の生態系と生物多様性の現況と評価
IV 知床世界自然遺産地域の利用状況と評価
V 知床世界自然遺産地域の管理の実行状況
VI 総合評価
付録
1. 知床世界自然遺産地域の平成23年度レクリエーション利用状況
2. その他の開発行為
3. 平成23年度実施ハード事業
4. 平成23年度実施ソフト事業
- (1) 海洋観測ブイによる水温の定点調査
- (2) ケイマフリ・ウミネコ・オオセグロカモメ・ウミウの生息数、営巣地分布と営巣数調査
- (3) エゾシカの影響からの植生の回復状況調査(林野庁1ha囲い区)
- (4) エゾシカの影響からの植生の回復状況調査(環境省知床岬囲い区)
- (5) 密度操作実験対象地域のエゾシカ採食圧調査
- (6) エゾシカ及び気候変動等による影響の把握に資する植生調査
- (7) シレトコスミレの定期的な生育・分布状況調査
- (8) エゾシカ越冬群の広域航空カウント
- (9) 陸上無脊椎動物(主に昆虫)の生息状況(外来種侵入状況調査含む)
- (10) 中小大型哺乳類の生息状況調査(外来種侵入状況調査含む)
- (11) 河川内におけるサケ類の遡上数、産卵場所および産卵床数モニタリング
- (12) 利用実態調査
- (13) ヒグマの目撃・出没状況、被害発生状況に関する調査
- (14) オオワシ・オジロワシ飛来状況調査
- (15) シマフクロウに関する調査
- (16) 航空機による海氷分布状況調査
- (17) 「北海道水産現勢」からの漁獲量変動の把握
- (18) スケトウダラの資源状態の把握と評価(TAC設定に係る調査)
- (21) 海水中の石油、カドミウム、水銀などの分析
- (22) エゾシカの主要越冬地における地上カウント調査(哺乳類の生息状況調査を含む)
- (23) エゾシカの間引き個体、自然死個体などの体重・妊娠率など個体群の質の把握に関する調査
5. 普及啓発イベント一覧
6. 普及啓発資料一覧
7. 各種会議等の開催状況
8. 事務所一覧
(9) 陸上無脊椎動物(主に昆虫)の生息状況(外来種侵入状況調査含む)
| 資料名 | 平成23年度知床生態系維持回復事業エゾシカによる昆虫類への影響調査業務 |
|---|---|
| 調査主体・事業費 | 環境省・約300万円 |
| 評価項目 | 遺産登録時の生物多様性が維持されていること。 エゾシカの高密度状態によって発生する遺産地域の生態系への過度な影響が発生していないこと。 |
| 評価指標 | 動物相、生息密度、分布 |
| 評価基準 | 登録時の生息状況・多様性を下回らぬこと。 外来種は、根絶、生息情報の最少化。 |
<平成23年度の具体的調査手法>
エゾシカ個体数の増加による昆虫類の変化の把握(昆虫類モニタリング調査)は、3季にわたり、知床岬地区の山地高茎草本群落、ガンコウラン群落、亜高山高茎草本群落の草原植生保護区及び森林調査区、幌別地区の森林調査区の保護柵内外、岩尾別地区の森林調査区の保護柵内外、羅臼地区の植生モニタリングサイトを調査地として、ピットフォールトラップ、ボックスライトトラップ、スウィーピング法による現地調査を実施し、昆虫相の現状についての定量的な把握を行った。
| 調査方法概要 | 実施状況 |
|---|---|
【ピットフォールトラップ】 ・地面と同じレベルに開口部がくるようにプラスチックコップを設置し、落下する昆虫類を採集する方法。 ・地表性歩行虫類(オサムシ科甲虫等)を対象として実施した。 ・設置個数は草地環境10個、樹林環境20個とした。 ・防腐剤として20%酢酸を入れ、2晩設置した後に回収した。 ・回収後には埋め戻しを行い、環境の復元に努めた。 |
 |
【ボックスライトトラップ】 ・夜間に照明を点灯し、集まる昆虫類を採集する方法で、光源に寄ってきた虫が漏斗部から下の捕虫器に入る仕組みになっている。 ・走光性昆虫類(蛾類等)を対象として実施した。 ・樹林環境で実施し、1地点あたり1個設置した。 ・誘引光源は 6Wの紫外線灯1本とし、夕方設置、翌朝に回収した。 |
 |
【スウィーピング】 ・捕虫網を振り、草や木の枝の先端や、花を払うようにしてすくいとることで、木や草、花の上の昆虫類を捕まえる方法。 ・植食性昆虫類等、昆虫類全般を対象とした。 ・草地環境、及び、樹林環境では林床部で実施した。 ・1地点あたり2人×15分の作業量を基本とした。 ・特に植生保護柵内では植物を損傷しないよう注意して実施した。 |
 |
<平成23年度の具体的調査データ>
本調査では、ピットフォールトラップの結果に基づくクラスター分析の結果、①ガンコウラン群落、②亜高山高茎草本群落、③森林調査区及び羅臼の樹林地に区分され、また、亜高山高茎草本群落は、ガンコウラン群落よりも、樹林環境に類似していることが示された。
ボックスライトトラップでは、蛾類を対象として、食性区分毎の各種の出現状況について柵内外での比較を行い、月によって差はあるが、柵内で各食性区分ともに個体数が多い傾向が認められた。
スウィーピング法では、訪花性の昆虫類に着目し、ハエ目のハナアブ科、ツヤホソバエ科とハチ目のヒメハナバチ科、ミツバチ科、コハナバチ科を今後のモニタリングの指標として同定、整理を行った。また、調査地点における植生状況を把握し、植生との関係を柵内外で比較し、地点によって差はあるが、柵内での昆虫類相が多様である傾向を示した。
全体で9目93科444種の昆虫類が確認された。地点により差はあるものの、何れの地点においても、エゾシカ生息の影響を強く受けている植生保護区や森林調査区の柵外と比べ、影響後の回復過程にある柵内で若干、多くの種が確認された。また、影響をほとんど受けていない環境として設定した羅臼地区では、エゾシカの影響が少なく、下層植生も豊富に生育している環境を反映し、他の樹林環境の柵内とほぼ同等の出現種数であった。
表 ピットフォールトラップ調査結果
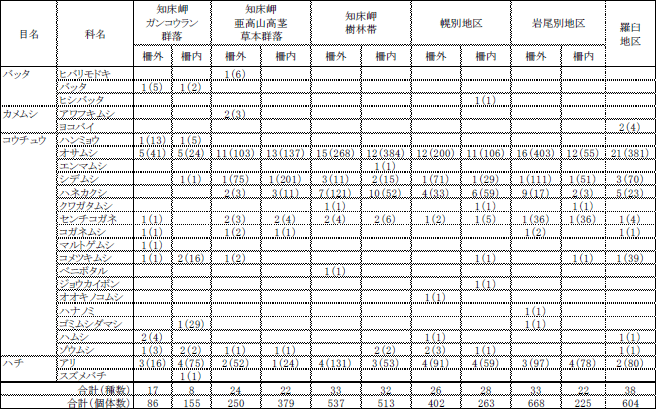
※表中の数値は種数、()内は個体数を示す。
<コメント>
柵内外における昆虫類の群集構造の違いは、保護柵内では植生が回復傾向にあり、柵外と比較し、多様な植物が生育しつつあること等を示していると考えられた。
昨年度調査及び本調査によって示された植生の変化に伴う昆虫類の群集構造の変化は、植生回復の初期段階におけるものである。今後、知床半島における昆虫類を含めた生態系全体の変化は、経年的に把握していくことが望ましく、世界遺産に登録された知床半島の基礎調査データのひとつとして貴重なものと考えられる。















